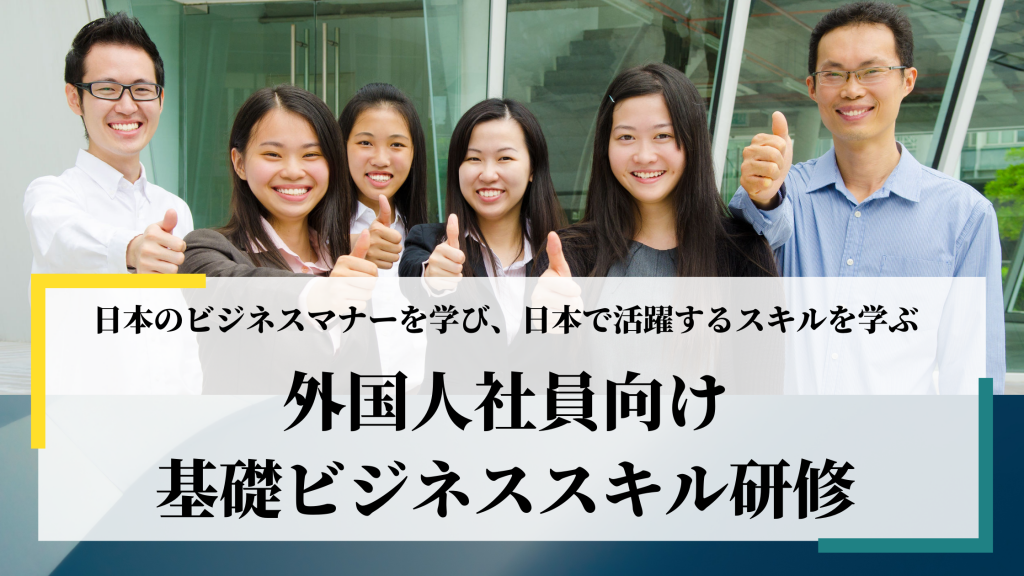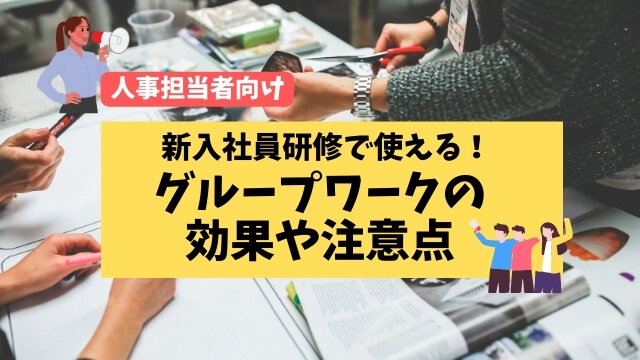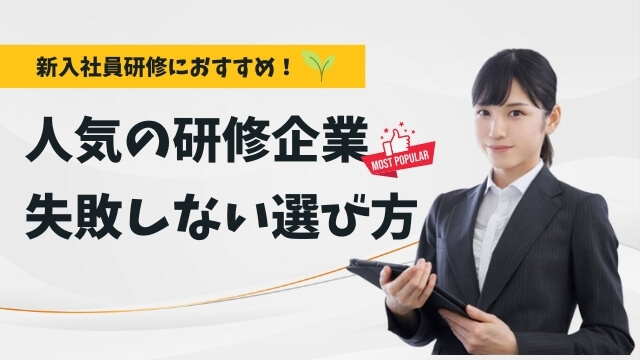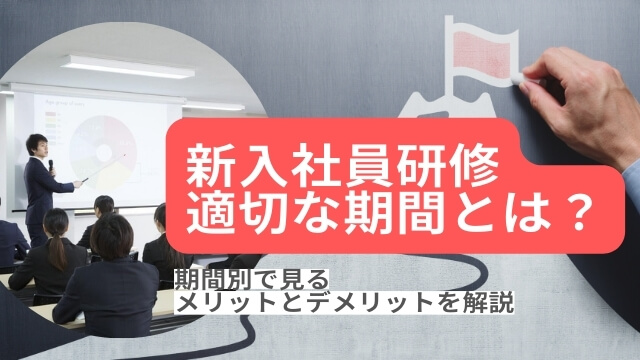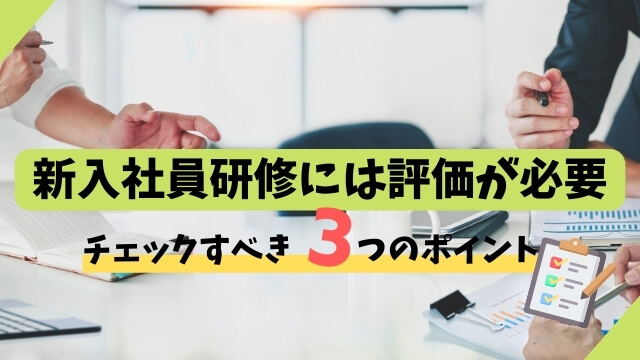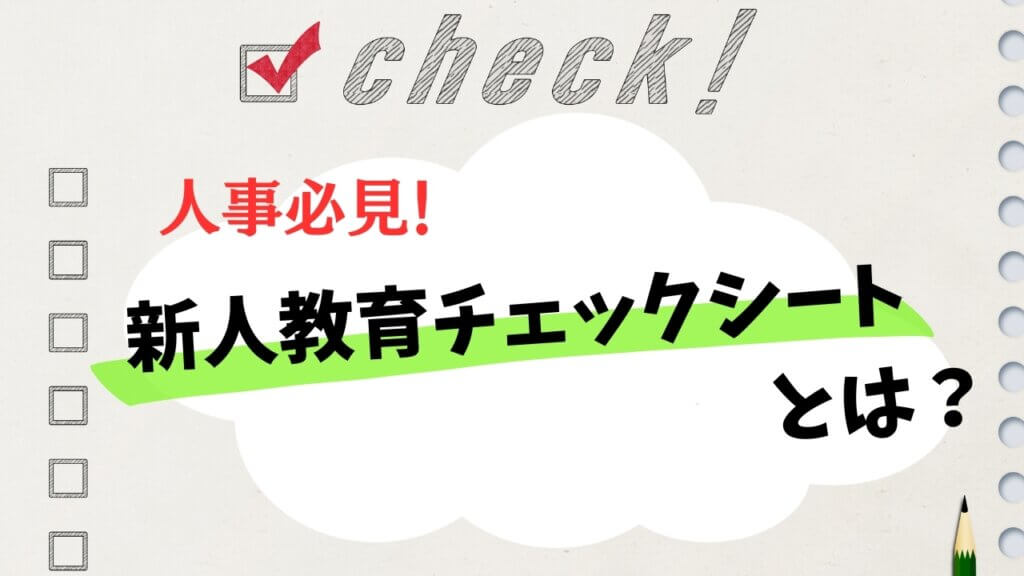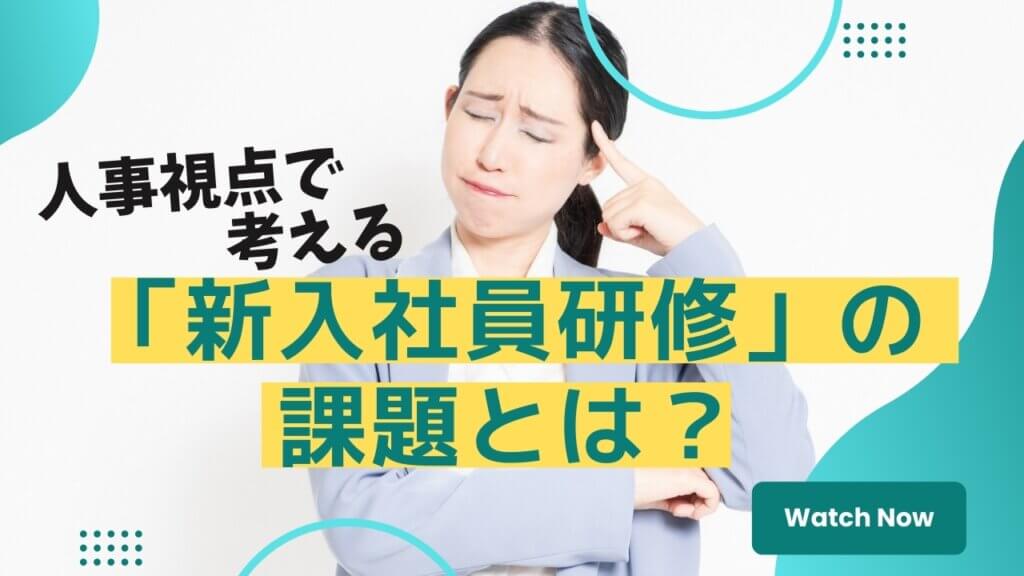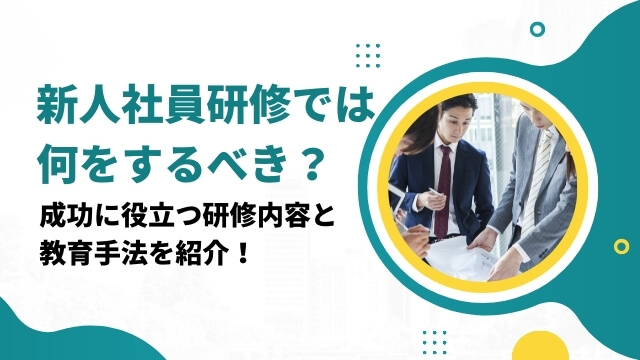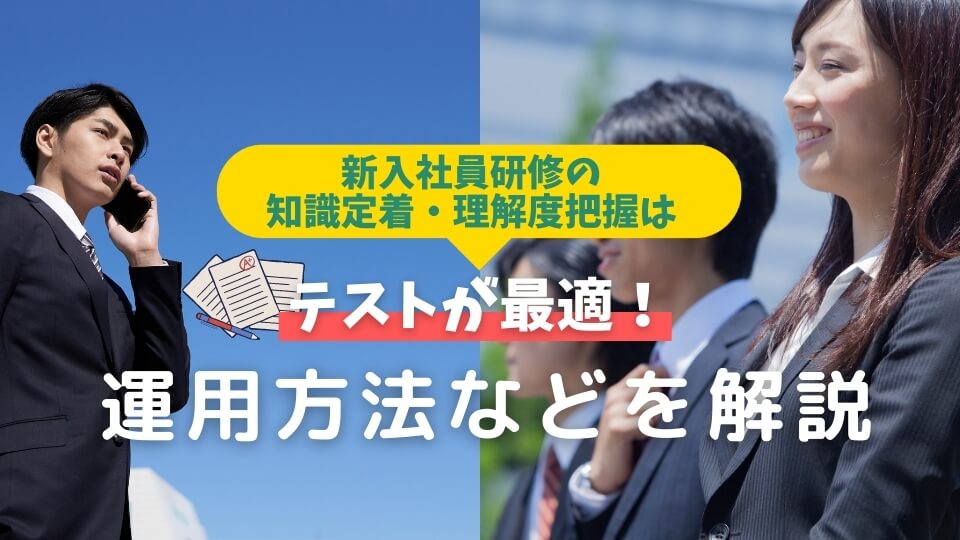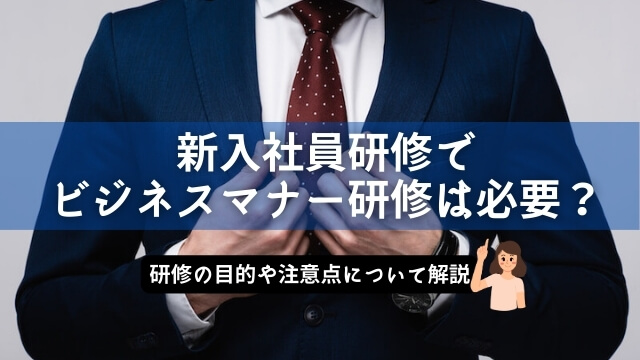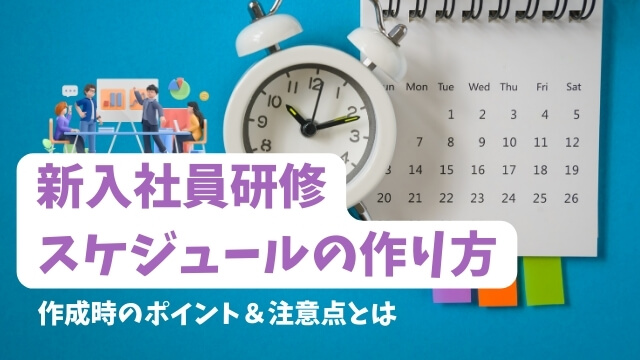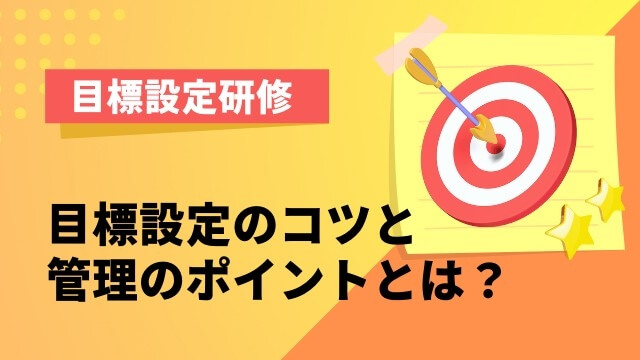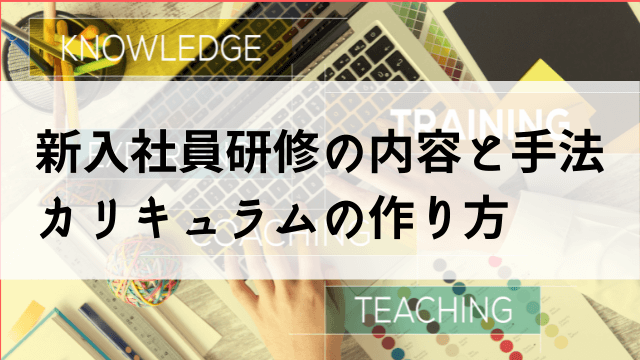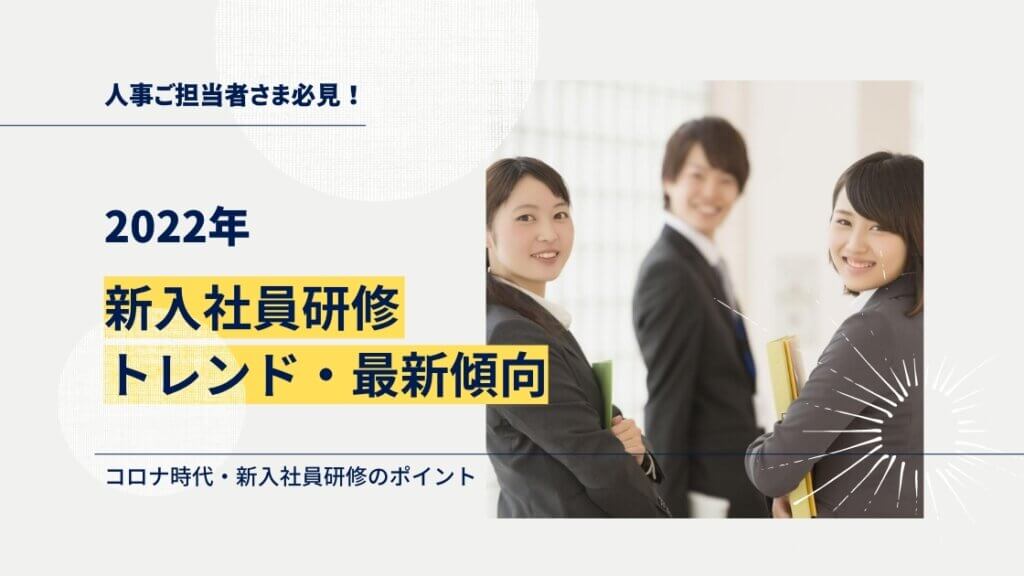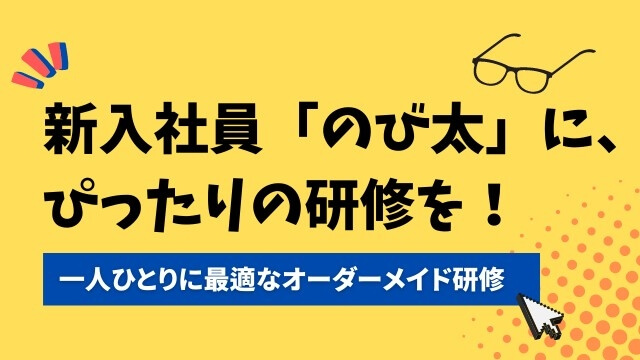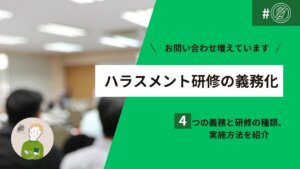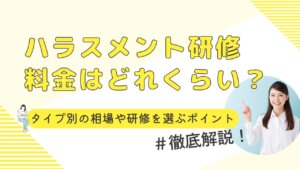労働組合は時代遅れ?若者離れの原因や影響、活動意欲を高める方法を解説
「労働組合の若者離れが進んでいるが、企業の発展のために何とか解決したい」と考えている担当者の方もいるのではないでしょうか。若者離れの解決につながる手段はいくつかあり、具体的には研修やレクリエーションなどの開催が挙げられます。
本記事では、労働組合の若者離れを解決するために理解すべき組合の現状や、若者離れが進む背景を解説します。労働組合の若者離れを解決する対策や研修の活用方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
労働組合の若者離れが進む3つの理由

近年、労働組合では「若者離れ」が深刻な問題となっています。その背景には、次の3つの理由があると考えられます。
- 若者の価値観と労働組合のギャップ
- 組合に対するイメージと実態のズレ
- 労働環境の変化と組合の対応
若手社員の組合参加を促すために、若者が組合から距離を置いてしまう原因を把握しておきましょう。
若者の価値観と労働組合のギャップ
企業で「若者」とされる20〜30代前半はZ世代に該当し、個人主義的な価値観が強い傾向にあります。さらに、仕事とプライベートのバランスを重視し、必要以上の集団活動や交渉ごとを避ける傾向もみられます。
そのため、労働組合のように集団で団結し、交渉を通じて権利を守るスタイルに対して、「自分には合わない」と感じる若者も少なくありません。価値観が合わない組織とは一定の距離を保とうとするため、組合の活動に関心を持たない若者が増えていると考えられます。
組合に対するイメージと実態のズレ
若者が抱く労働組合に対するイメージと、実際の活動内容との間にズレが生じていることも、若者離れの一因となっています。
電機連合が2005年6〜7月にかけて労働組合離れの原因を調査したところ、「組合が何をしているのかわからない」と回答した人が30.7%にのぼりました。
労働組合では労働条件の改善や、福利厚生の充実など若手社員にもメリットのある活動に取り組んでいます。しかし、その活動内容が十分に浸透していないため、組合に参加することを躊躇する若者が多い状況です。
出典:労働調査協議会・労働調査「若手組合員に労働組合をわかってもらう方法を考える」
労働環境の変化と組合の対応
若者をはじめとする労働者を取り巻く環境の変化も、労働組合から距離を置いてしまう原因です。
これまでは、正社員を中心とした組織づくりや活動が前提とされてきました。しかし、働き方が多様化した近年では、非正規雇用者や業務委託労働者などが増加し、組合の対応にも変化が求められています。
変化に対応できない組合は、新しい働き方を求める若者のニーズに応えられません。そのため、組合への関心を低下させる可能性があります。若者の参加を促すには、時代に即した柔軟な運営が必要です。
労働組合の若者離れが与える影響

厚生労働省が実施した「令和6年労働組合基礎調査」によると、2024年6月末時点での労働組合の推定組織率は16.1%でした。労働組合数と組合員数も減少傾向にあり、社会全体で労働組合の若者離れが進んでいるとわかります。
ここでは、労働組合から若者が離れてしまうとどのような影響があるのかを解説します。
出典:厚生労働省「令和6年労働組合基礎調査の概況・労働組合及び労働組合員の状況」
労働組合への影響
労働組合における若者の減少は、組織全体の活力と交渉力の低下を招きます。このほか、労働環境の改善や労働者の権利擁護が難しくなるケースもあるでしょう。
組合員数の減少は、労働条件の向上や社会的な影響力の低下を意味します。結果として、組合の存在意義が問われる可能性もあります。また、若年層の参加が減ってしまうと組織の高齢化が進むため、新しい働き方や価値観への対応が遅れてしまうこともあります。
労働者への影響
若者離れが進むことで、労働組合の組織力は低下し、労働環境の悪化を招く恐れがあります。労働組合が弱体化すると、交渉力が低下するため、次のような深刻な影響を受ける可能性もあります。
- 賃金や労働条件の悪化
- 雇用の不安定化
- 労働環境の悪化
さらに、適正な労働環境で働けない若者は、正しい労働法やワークルールを学ぶ機会を得ることができません。その結果、労働者としての権利を守る術を知らず、労働環境の悪化を自ら受け入れてしまう可能性があります。
若者が誤った働き方を受け入れてしまうことで、その影響が広がり、社会全体に不健全な労働文化が蔓延するリスクがあります。
労働組合で若者離れを改善する方法

労働組合で若者離れが解消されれば、組織力の強い組合を醸成でき、労働条件や環境の改善が見込めます。若者離れを改善する代表的な方法は次の3つです。
- 若手中心の労働組合を設置する
- 組織活動のデジタル化を進める
- 研修やイベントを開催する
労働組合の若者離れを解消できれば、若者の価値観に寄り添ったより良い労働環境が実現できます。
労働組合では「オルグ」と呼ばれる組織力を高める活動が行われます。オルグについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

若手中心の労働組合を設置する
従来の労働組合とは別に若手中心の労働組合を設置すれば、若者離れの改善を促せます。
若手中心の組合を設けることは、組合活動の参加障壁を下げる、組合リーダーとしての経験を段階的に積む機会が得られるなどのメリットがあります。また、若者が主体となって組合活動の企画や運営を行えるため、自分たちの価値観を反映した活動がしやすくなるでしょう。
また、年長者の視線を気にする必要もありません。そのため、率直な意見交換ができたり、若手ならではの視点を取り入れられたりと組合活動の革新にもつながります。
組織活動のデジタル化を進める
組織活動のデジタル化も、労働組合の若者離れを改善させるきっかけになります。
これまでは、組合の機関紙や集会などを利用して情報発信をするのが通例でした。情報発信手段をWebサイトやSNSなどに移行すれば、デジタルネイティブ世代といわれる若者はより手軽に組合の情報を収集できるようになります。
また、コミュニケーション手段をデジタル化に変更することも若者離れの改善につながります。Web会議ツールやチャットツールを利用すれば、より効率的にコミュニケーションがとれるようになるでしょう。
また、組合活動そのものもオンライン学習やe-ラーニングへ転換できます。組合員それぞれの都合に合わせて活動に参加できるようになれば、タイムパフォーマンスを重視する若者からの支持も集めやすくなります。
研修やイベントを開催する
研修やイベントを開催することも、労働組合への加入を促せる方法です。
労働組合が主催する研修では、人事や労務など組合員として把握しておきたい内容を取り扱うケースが多くあります。正しい知識を身につけられれば、労働環境の改善や適切な環境の維持に役立ちます。組合員の業務スキル向上を目的としたビジネスマナーや知識をテーマにした研修の開催も効果的です。
また、イベントやレクリエーションの実施は、組合活動への興味・関心を高めることにつながります。組合員以外も参加できるイベントを開催すれば、参加した社員の入会検討や新規組合員の獲得が見込めます。
ただし、内容によっては若手社員が組合に対してネガティブなイメージをもつきっかけになるかもしれません。組合への入会検討につながったり、組合員が参加意欲を高めたりする魅力的な企画の選定が重要です。
労働組合が主催する研修やイベントについては、こちらの記事を参考にしてください。


若者の価値観を理解し時代に合った組織運営をしよう

労働組合の若者離れを防ぐには、現代の若者の価値観やニーズを理解し、それに適応した組織運営を行うことが欠かせません。
現代の働き方は多様化しており、正社員だけでなく、非正規雇用やフリーランスとして働く人も増えています。こうした変化を踏まえ、誰もが参加しやすい仕組みをつくる必要があります。
若者の考えや意見を知るには、積極的に若手社員との対話を重ねましょう。そのためには、デジタルツールを活用した柔軟なコミュニケーションや情報発信を強化し、若手社員が関わりやすい環境を整えていく必要があります。
若手社員の特性を理解したい方には、以下の記事がおすすめです。ぜひ、ご覧ください。

まとめ

労働組合から若者が離れてしまう原因には、価値観の違いや、組合に対するマイナスなイメージ、労働環境の変化などが挙げられます。新入社員や若手社員の加入を促進するためには、若者の価値観を受け入れて、柔軟な組織運営を行うことが重要です。
若者が関心を持ちやすいテーマで研修やイベントを開催し、労働組合の役割やメリットを伝える機会を増やしましょう。また、SNSやデジタルツールを活用して情報を発信し、若者が気軽に参加できる環境を整えることも効果的です。
ガイアシステムではスキルアップやビジネスマナーに関する研修はもちろん、組合の広報活動に役立つ研修の提案が可能です。新入社員向けの研修にも対応していますので、ぜひご検討ください。
新入社員向け 研修カリキュラム
迷ったら、まずこの研修カリキュラム
入社員スタートアップ研修 |基本ビジネスマナー習得
ビジネスの根底を作る、社会人としての基礎づくり
新入社員9つの基本行動|社会人としての成長の基盤づくり
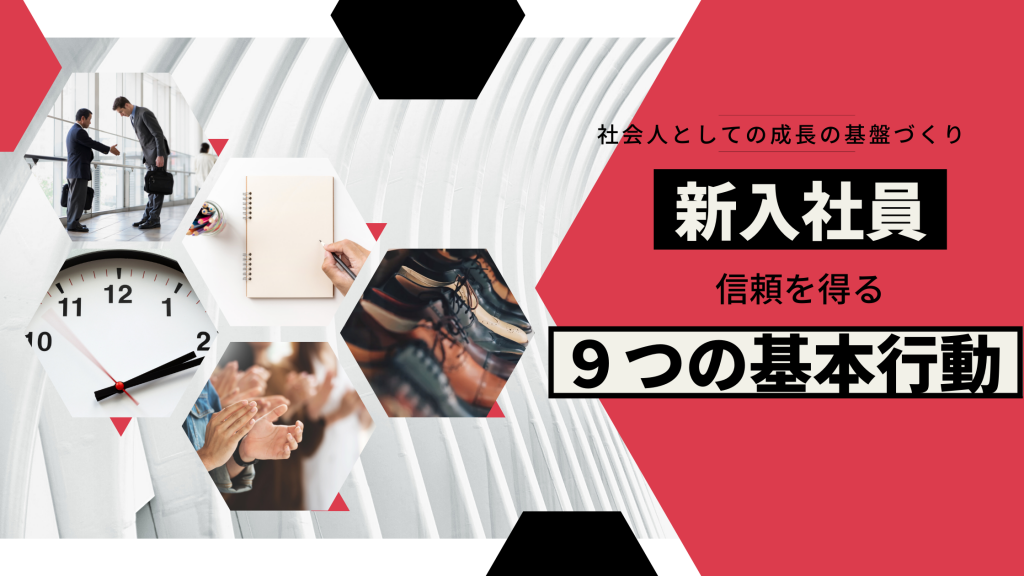
「挨拶」や「履物を揃える」「時間を守る」など人として大切な“基本行動”を凡事徹底することを指導する研修です。
何歳になっても、どのような役職や立場になっても、相手の立場に立った行動を継続できることが、社会人生活を充実させ自身を成長させるために必要です。
本研修では、ビジネスマナーの根底にある考え方と、コミュニケーションの要諦をお伝えします。
新人が結果を出すための実践的メソッド
入社1年目からの仕事の流儀(前編・後編)
社会人として基本的なビジネスマナーを学ぶ「新入社員スタートアップ研修」とは違い、[
仕事の流儀シリーズ」では新入社員や若手社員が仕事で成果を出すための実践的なメソッドを“前編”と“後編”に分けてカリキュラムを構成しております。
前編では、新入社員や若手社員が特に躓きやすい「報連相」「タイムマネジメント」「失敗の向き合い方」「オンラインマナー」後編では、仕事の質を高める「会議の参加の仕方」「コスト意識」「質問探求力」「気配り心配り」をカリキュラム化しています。

「新人・若手社員として課題が出やすいテーマ」から更に一歩踏み込んだ、日常のビジネスシーンにおいて成果に繋がる実践術・活用術を学びます。新入社員や若手社員の皆様が明日から活用できる気づきとスキルアップを目的とした研修です。