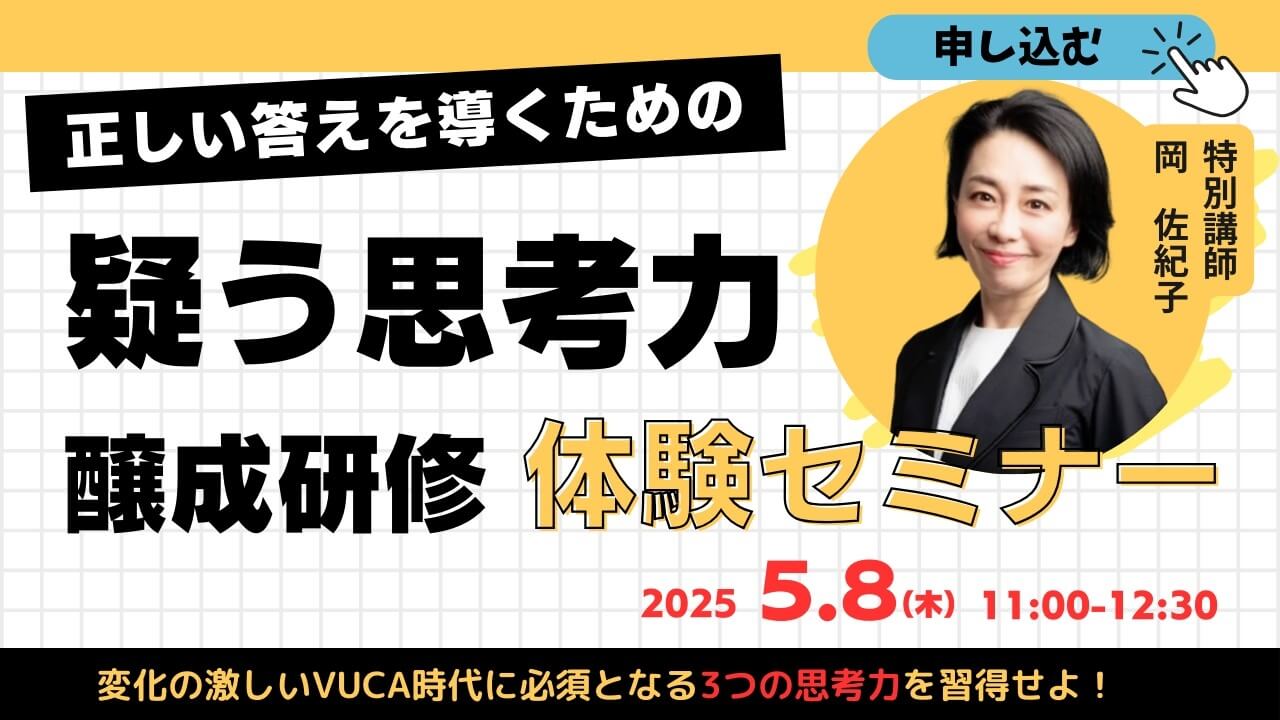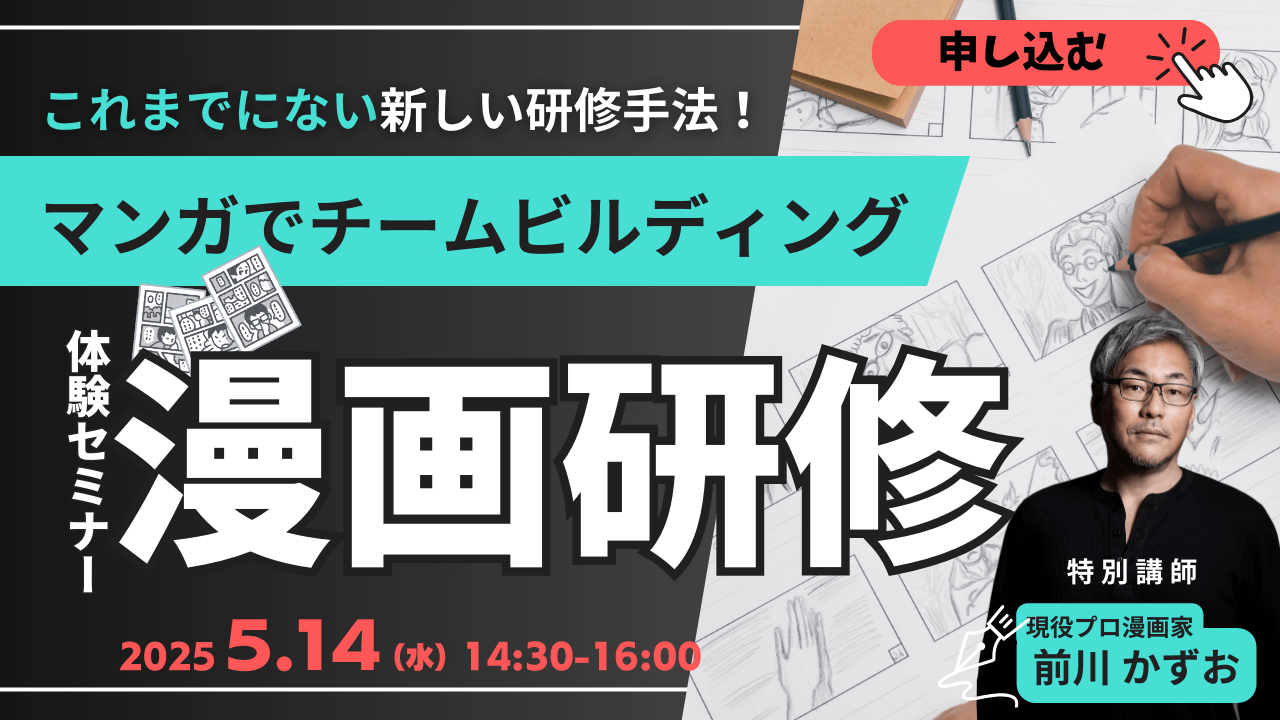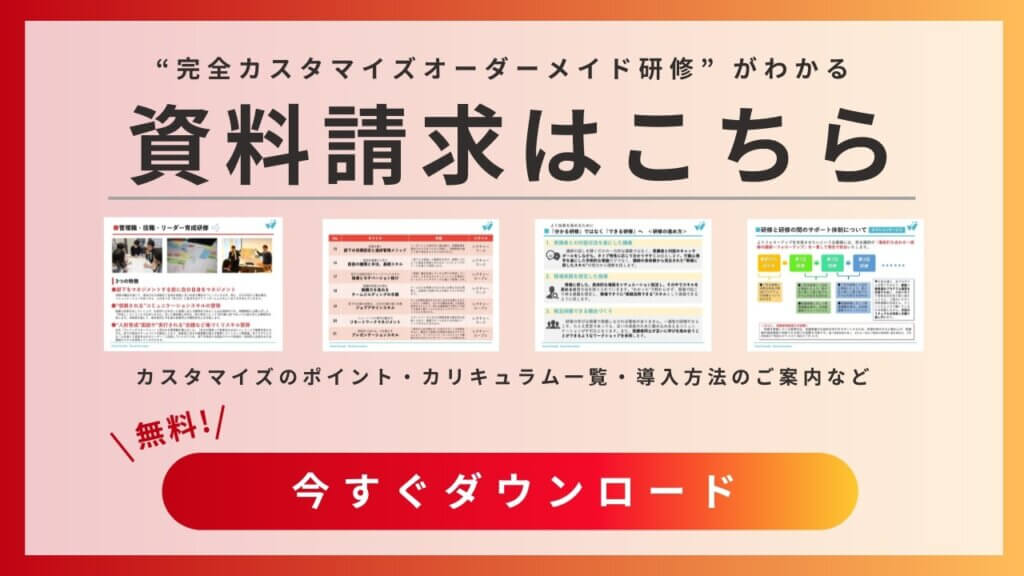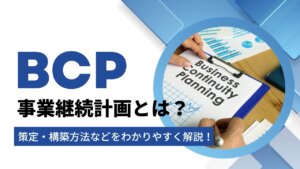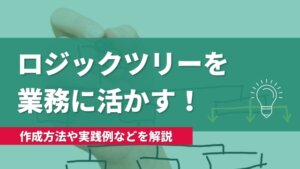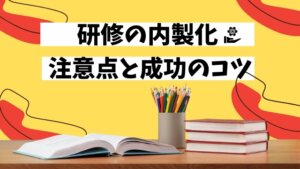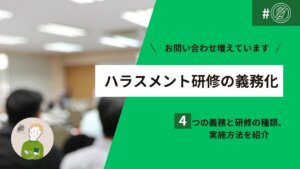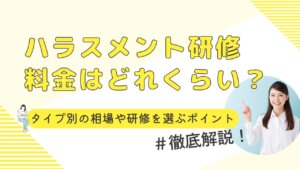BCPとは?事業継続計画の策定・構築方法などをわかりやすく解説!
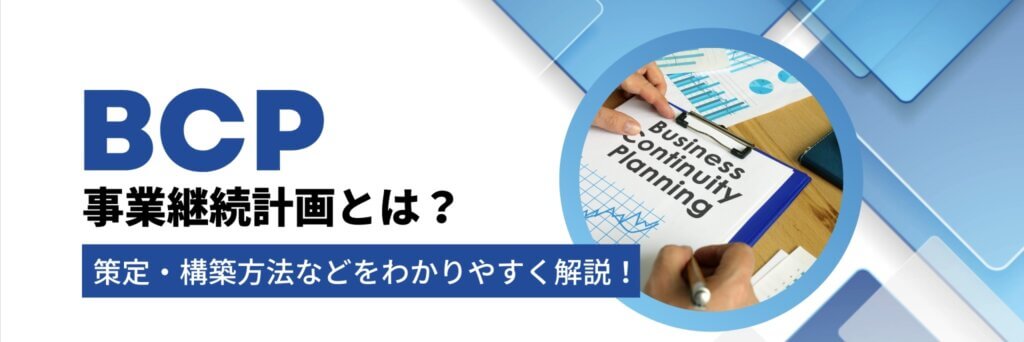
近年、自然災害やあらゆる緊急事態によるリスクから企業を守るための計画として「BCP(事業継続計画)」の策定・構築が重要視されています。しかし、「そもそもBCPって何?」「なぜ策定する必要があるの?」といった疑問であったり、「うちは大企業ではないから、必要ないでしょう」とお考えの方がおられるのではないでしょうか。

BCPの基本から策定する理由をはじめ、構築・策定によって損害を最小限に抑え、事業の早期復旧や継続につなげるためにやるべきことを解説します。自社でのBCP策定・構築の参考にしてみてくださいね。
BCP(事業継続計画)とは
BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)は、企業や組織が予期せぬ災害や事故に直面した際にも、重要な業務を継続または迅速に復旧し、事態を最小限に抑えるための戦略のこと。
地震、台風などの自然災害から、サイバー攻撃、パンデミックまで、様々なリスクに対応し、企業の存続と社会的責任を果たすことを目的としています。
BCPでは、重要業務の特定、目標復旧時間の設定、リスク分析と対策、緊急時の対応手順、必要資源の確保などが定められます。適切なBCPを策定・運用することで、緊急時の混乱を最小限に抑え、顧客や取引先からの信頼を維持し、財務的損失を軽減できるだけでなく、従業員の安全も確保できます。
今日のビジネス環境において、BCPは企業の競争力と持続可能性を高める重要な経営戦略ツールと言えます。

BCPは単なる緊急時対応計画ではなく、平常時からの準備、緊急時の対応、そして事業復旧までを包括的に網羅する戦略的なアプローチのことを指します。
企業のあらゆるリスクに対応するための計画
日本では自然災害が増えているだけでなく、新型コロナウイルスの感染拡大やネットワークが発展することによる障害やテロなど、企業を取り巻くリスクは多様化しています。事業が継続できなくなると、取引先や顧客からの信頼を失ってしまうことがあります。
しかし、こういったリスクはいつ発生するかわかりません。そのため、リスクへの対応を誤ったり判断が遅れてしまうと社会的な信用を失ってしまったり最悪の場合には倒産ということも考えられるでしょう。緊急事態が起こった時に早急に復旧作業に入り、内的・外的リスクをできるだけ取り除くための体制づくりとして、BCPは注目されています。
BCP(事業継続計画)の重要性
BCP(事業継続計画)は、企業が直面する多様なリスクに対して効果的に対応し、持続可能な運営を確保するために不可欠です。
BCPは単なる計画ではなく、企業の持続可能性と競争力を高めるための戦略的なツールです。企業はBCPを通じてリスク管理能力を強化し、信頼性を維持しつつ、業務継続性と従業員の安全を確保することが求められています。
リスク管理を強化できる
現代のビジネス環境では、自然災害、感染症、サイバー攻撃など、さまざまなリスクが企業に影響を及ぼします。BCPを策定することで、これらのリスクを事前に特定し、迅速かつ効果的に対応するための手順を整えることができます。例えば、2011年の東日本大震災では、多くの企業がサプライチェーンの脆弱性を痛感し、BCPの重要性が再認識されました。
信頼を維持できる
緊急時においても適切な対応ができる企業は、顧客や取引先からの信頼を維持しやすくなります。
BCPが整備されていることで、顧客は企業が危機管理能力を持っていると認識し、取引先との関係も強化されます。特に、サプライチェーン全体でのBCPの重要性が高まっており、自社だけでなく取引先のBCPも考慮する必要があります。
業務中断の最小化できる
BCPは、重要業務を継続または早期に復旧させるための具体的な手順を提供します。これにより、緊急事態発生時でも業務の中断を最小限に抑えることが可能です。
例えば、富士通グループはサプライチェーン全体のBCM(事業継続マネジメント)強化に取り組んでおり、その結果として取引先との連携を深めることで業務継続性を高めています。
財務的損失を軽減できる
適切なBCPによって緊急時の損失を最小限に抑えることができます。
事業が中断した場合でも迅速な復旧が可能であれば、収益損失や顧客喪失といった財務的影響を軽減できます。また、BCP策定による税制優遇や金融支援などもあり、中小企業にとっては特に重要です。
従業員の安全を確保できる
BCPは従業員の安全確保にも寄与します。緊急時には従業員やその家族の安否確認や避難計画が必要です。BCPによって明確な行動指針が示されることで、従業員は安心して業務に取り組むことができ、その結果として企業全体の生産性向上にもつながります。
クライシスマネジメント研修 | これからの時代に必要な危機管理とは

リスクが顕在化した際の危機対応能力を向上させるための「クライシスマネジメント研修」
緊急時の意思決定、情報管理、ステークホルダーとのコミュニケーションなど、クライシス時に必要なスキルを習得します。
カリキュラム(一例)
- 企業にとってのクライシスとは
- クライシス事例と対応方法
- 自然災害・事故・事件・不祥事
BCP策定の目的

次に、各企業がBCPを策定・構築する目的や似ているものとの違いを理解しておきましょう。
BCPと似た言葉には「BCM」や「防災計画」があります。これらを正しく把握しておくことで、より効果的にBCPを策定・構築できます。
- 緊急時に適切かつ冷静な対応ができる
-
BCPは、リスクの大きさにかかわらず事業縮小や倒産の可能性を下げ、適切かつ迅速な行動につながります。
逆に、計画が自社の現状に合っていないものや曖昧になってしまっていると、被害を広げてしまうこともあるため注意が必要です。 - 経営戦略に役立つ
-
BCP策定・構築を行う中で、事業復旧の優先順位や組織として重要視していることが可視化され、共通認識を持つことができます。
その結果として、企業としての経営戦略の見直しができたり、業務の洗い出しが可能となります。
BCPと似ている言葉の違い
BCPと似ている言葉には、「BCM」や「防災対策」があります。子では、それぞれの違いについて解説します。
BCPとBCM
まずは、BCMについてです。
BCMとは、「事業継続マネジメント」の略で、BCPもそこに含まれています。
BCPは、策定・構築後の運用が重要になります。
そのため、BCPを策定する前の分析や運用など、総合的にマネジメントできるような体制づくりも必要になります。
BCPと防災対策の違い
防災対策は、自然災害や緊急事態などによる被害を可能な限り回避・軽減することで、人命や自社の財産を守ることが目的です。それに対して、BCPは緊急事態などが発生した後に「どのように事業を継続するか、早期普及させるか」というポイントに重点をおいています。
防災対策は「事前に防ぐためのもの」、BCPは「事後の対策である」ということを意識しておくと、それぞれの計画立案時にブレることがないでしょう。
BCP策定のメリット

ここからは、BCPを策定・構築するメリットを解説します。
BCPの具体的なメリットとしては、次のようなものがあります。
企業価値・社会的信頼の向上
BCP対策は、自社のイメージアップにつながります。
あらゆるリスクが緊急事態が起こっても、揺らぐことなく安定して事業の継続や経営ができるということ、対応方法やスピードの速さは企業としての評価や価値が向上するでしょう。
そのため、BCPの策定は緊急時のリスク対策だけに留まらないと考えられます。BCPが策定・構築できているかどうかは取引先の拡大につながるという点もメリットです。
従業員の意識向上と迅速な行動が可能になる
BCPを構築しておくことで、従業員のそれぞれが「緊急時に自分は何をすれば良いか」を考え、無駄なく迅速に行動することができるようになります。
特に、内的リスクへの対応が必要な場合、一つひとつの行動に世間が注目する可能性があります。スピードや動きに無駄がないこと、社会的信用を失う可能性を減らせるような計画立案を立てることで、逆に信用を高めることも期待できるため、しっかりとBCPを立案しましょう。
従業員が安心して働ける環境づくりにつながる
「なぜBCPの策定・構築が必要なのか」という疑問を抱く方もいるかもしれません。
リスクへの対策ミスなどによって、事業の縮小や倒産になってしまうと、働いていた従業員は仕事を失うことになります。
自社がリスクへの対策をしっかりできているのか、BCPが構築できているかどうかは、就職を考える際の評価に関わるかもしれません。今後、業界によってはBCPの策定が義務化(2024年の介護業界など)されることも考えられるため、早い段階で時間をかけて策定・構築しておくようにしましょう。
BCP策定・構築の注意点

BCPは、メリットばかりがあるわけではありません。
「策定・構築すればOK」というわけではなく、注意しておかなければならない点があります。
BCPの内容が自社の現状に合っているかどうか
まず、BCPの内容が自社に合っており、「実際に緊急事態が起こった時に効果を発揮するかどうか」を時間をかけて考えなければなりません。
BCP策定・構築は、自社にあった計画を立てることが何よりも大切です。
立案した計画は自社の現状に合っているのか、その計画に合わせて従業員は適切な行動ができるかどうか、その点を意識した計画作りが求められます。
BCPが機能しないことがある
BCPの策定・構築を考えるにあたり、「策定・構築すること」がゴールになってしまうケースは珍しくありません。
しかし、BCPは具体的に従業員が適切な行動を取れるかどうかが重要です。
「作ること」そのものがゴールになってしまうと有事の際に機能しないことも考えられるため、策定・構築したBCPの運用イメージも意識しておくようにしましょう。
BCP策定・構築の流れ
では、実際にBCPを策定・構築する際の流れを確認しておきましょう。
一つひとつのステップを丁寧に踏んでいけば、自社の現状に合った機能的なBCPができあがります。
まず、自社としての方針を決めましょう。
BCPによって目指すこと(最終目標)、何を実現するかなど、経営層から従業員に至るまで幅広く意見を集めて作ることで、全員が同じ方向性を持つことができるようになります。
基本方針が定まったら、実際に策定していきます。
策定する際に決めること、考えるべきことは次のとおりです。
- リスクの分析と評価
- 重要資源の整理
- 優先度が高い中核事業の選定
- 目標復旧時間の設定
リスクの分析と評価については「事業影響度分析(BIA)」によって”自社でどのような影響が発生するのか”、”その影響はどのような時系列で進んでいくのか”を分析します。
そして、自社にとって重要であると考えられる資源(人的なもの含む)を整理した上で、「継続するべき事業」の優先順位を決めていきます。BCPにおいては、優先順位の高いものや影響度の低いものから復旧させることで、事業の継続を測ることになります。
なお、復旧までの目標時間については実現可能な、具体的な時間で設定するようにしましょう。従業員の負担が強くなると、復旧したもののその後の継続が難しくなってしまうことも考えられます。「継続」と「立て直し」は全く違うということを意識しておきましょう。
BCPの策定ができたら、具体的な戦略を検討します。
BCSとは「事業継続戦略」の頭文字をとったものであり、「目標復旧時間」などを元に達成可能な戦略を立案します。
そして、自社の現状と照らし合わせた上で実行可能かどうかを評価し、選定します。
自社の現状は、常に変化しています。災害はいつ起こるかわかりません。
そのため、「いつ起こっても大丈夫」な計画を立てることを心がけ、「作成してあるBCPが一年前から変わっていない」ということのないよう、更新しつづけることが重要です。
人的リソースや経営課題、事業の優先順位など、定期的に見直して評価を行い、それをBCPに反映させるようにしましょう。
BCP運用のポイント

BCPは、策定・構築した後の運用が重要です。
「BCPがあることは知っているけれど、それが何かわからない」「内容はあまり覚えていない」ということでは、有事の際に適切な行動を取ることができず、結果としてBCPが意味をなさないことになってしまいます。
ここでは、BCP運用のポイントを解説します。
社内研修などによる周知・教育
BCPを策定・構築したら、社内研修などを企画・実施しましょう。有事の際の行動は、経営層だけが力を入れれば良いのではなく、組織全体が統一感を持って動くことでより迅速な復旧や社会的な信頼を取り戻すことができます。
誰かが方向性と違う行動をとると、「組織が言っていることややっていることと違う」と不信感を抱かれたり、信頼を失ってしまうことになりかねません。
BCPの内容や全員が覚えておくべきこと、組織としての方向性を確認しておくことで、例え明日に有事が起こったとしても冷静かつ適切な行動を取ることが期待できます。
評価と改善を繰り返すことで精度を高める
前述したとおり、BCPは常に変化する自社の状況に合わせて評価・改善していくことが必要です。
精度を高めるためには、様々な経験年数の従業員の意見を盛り込むことで、新しい視点を含めることが可能になります。同じメンバーで評価・改善を行うのではなく、組織全体を巻き込んで行うことを意識しましょう。
BCPに関する身近な取り組み
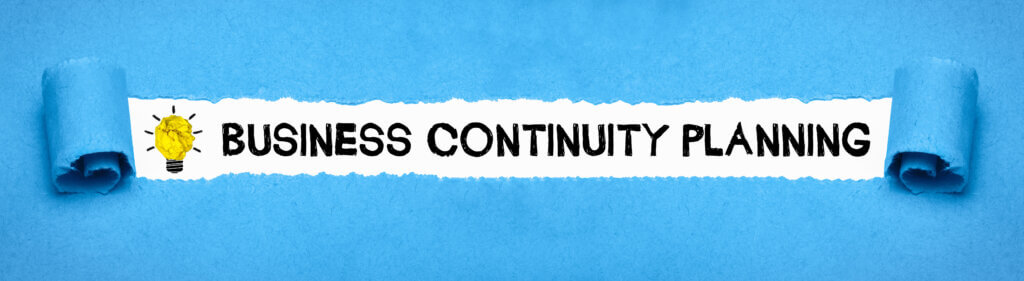
最後に、BCPに関する具体的な取り組みを紹介します。「すでにやっていること」と思われるかもしれませんが、立派なBCPになりますので、ぜひ参考にしてみてください。
テレワークの活用
ネットワーク環境を整え、出勤せず自宅などで働くテレワークは、新型コロナウイルスの流行によって一般的になりました。「自社外で働くことができる体制づくり」は、自然災害などで通勤ができなくなった場合でも必要な機器や環境さえ整っていれば災害前と変わらず業務を継続することが可能です。
出社を原則としなければならない業界やサービスがあるかもしれませんが、そのような場合でも「社外でできること」と「社内でしかできないこと」など業務の洗い出しを丁寧に行うことで、緊急事態が起こったときのダメージをできるだけ軽減し、顧客などに影響の少ないような体制を整えておきましょう。
なお、近年情報漏洩などの問題や事件が増えていますが、情報セキュリティや個人情報の管理対策をしっかりと行うことで、「いつ・どこにいても」変わらず仕事ができるような状態を作っておくことは、立派なBCPと言えます。
コミュニケーションツールの活用
テレワークに関連することですが、チャットツールなどの活用やビデオ会議システムによるコミュニケーションに慣れておくことも、BCPと言えます。
仕事において、従業員同士の非言語的コミュニケーションを大切にしている人もいるかもしれません。しかし、現在は文字ベースのコミュニケーションが主流になってきています。
そのため、チャットツールやビデオ会議システムなどに慣れておくことで、より良い関係性づくりや「これまでには意見が出せなかった人からの声」を引き出すことにもつながります。特に、コミュニケーションツールの進化によって全国や世界の人との連携が取れるようになっていることを考えると、様々なツールを活用することはBCPとして有効でしょう。
時差出勤
「テレワーク」が難しい業界やサービスについては、時差出勤を活用することによってリスクを分散することも考えられます。常にコミュニケーションをとりながら、業務の流れが途切れることのないようにしておくことで、事業の早期復旧や継続に繋げられると考えられます。
「決まった時間で就業すること」に慣れていると、時差出勤などに違和感を感じるかもしれませんが、これからの時代、いつ災害が起こるかわからないことを常に想定し、柔軟な対応が取れるようにしておくことが大切です。
BCPの策定・構築でより良い事業運営を!
今回は、企業規模に関わらず重要であるBCP(事業継続計画)について解説しました。
東日本大震災をはじめとして様々な災害が起こる現代では、いつ何事が起こっても冷静かつ適切な動きが求められます。事業の継続や早期復旧は、社内外の多くの人たちにとって重要なものです。まだ、策定・構築ができていない企業や組織の方々は、ぜひ明日からでも策定・構築のために動き出しましょう。また、「以前作ったがそのまま放置している」という心当たりのある企業・組織の方は、すぐに見直しをしてみてください。
最適なBCPで、より良い事業運営を行いましょう。